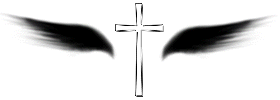
†††††††††††† 月が見てた ††††††††††††
静かに暮したいと願うのは、いけないことだろうか?
幸せでありたいと願う事は、いけないのだろうか?
人には、幸せになる権利があるのではないのですか?
私には、幸せになる権利はないのですか?
──罪もない多くの人を、死に追いやって……生きてきた私には、微かな幸せすら掴む権利は、ないのでしょうか?
1主人公:スイ=マクドール
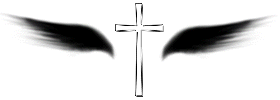
†††††††††††† 月が見てた ††††††††††††
静かに暮したいと願うのは、いけないことだろうか?
幸せでありたいと願う事は、いけないのだろうか?
人には、幸せになる権利があるのではないのですか?
私には、幸せになる権利はないのですか?
──罪もない多くの人を、死に追いやって……生きてきた私には、微かな幸せすら掴む権利は、ないのでしょうか?
「兄さんは、卑怯だわ。逃げてる。
才能を……誰かを助ける力があるのに、それを使わない兄さんは、弱虫だわ。」
囁いた言葉は、今も心に突き刺さっている。
彼女の……大切な妹の瞳は、キラキラと輝いていた。月明かりの下で、潤んで光っていた。
その意志ある瞳を見た瞬間、彼女はもう戻れない場所にいるのだと、知った。
伊達にこの呪われた血のなすままに、戦場に立っていたわけではない。
彼女が何を考え、何を決意したのか──そして、このじゃじゃ馬娘が、説得には耳を貸さないことを、よく知っていた。
だから、マッシュは目を閉じたのだ。
彼女の目を見ないように。自分の心に蓋をするように。
戦場から逃げて、手に入れた幸せを握るように、きつく……筆を握り締めて。
「ああ、そうだ。俺は弱虫だ。逃げた犬だ。──それの何が悪いというのだ?」
そうすることが、一番いいと思ったのだ。
そうしなければ、多くの罪なき命が失われると思ったのだ。
自分が仕えていた主君は、偉大な方であった。──偉大すぎるくらいに偉大であった。だからこそ、マッシュは耐えられなかったのだ。
自分が編み出した策が、間違えなく敵を殺した瞬間。目の前で、罪も無い少女が巻き込まれたあの瞬間……見てしまったその時を、マッシュは忘れる事ができないのだ。
「兄さんが逃げた事で、助かる命があったのかもしれないっ! でも、兄さんが闘う事で救われる命があると……どうして分からないのっ!? 兄さんの目は腐ってしまったのっ!? 見ればわかるじゃないのっ! この帝国をっ! この現状をっ! この村にはまだ何もないかもしれない。でも一歩外に出れば、そこはもう……腐りきった……──。」
「やめろ、オデッサ。」
唇で囁くように止めて、マッシュは机の上の紙をまとめた。
この村の子供たちが書いた字は、まだまだつたなくて、読みづらい事この上なかったが、それでもマッシュにとっては、愛しい字であった。誇りに思える字であった。
子供たちが字を学ぶ、言葉を学ぶ──そんな場がここにあること。こんな自分だからこそ、子供達に──次代の子供たちに教えられる事。
マッシュはそれがとても愛しいことだと思ったし、これは自分を生かす道だと想っている。未来を生かす道でもあると。
あんな血が血を呼ぶ戦場ではない、温かな血脈が感じるこの地が──自分の生涯を終える土地なのだ。
「もし私がお前に力を貸すとしよう。そうすると、反乱軍と帝国軍の対立は益々激しくなるだろう。」
「解放軍よ。」
マッシュの語り掛ける声を途絶えさせて、オデッサは修正を入れた。
彼女は後ろに流した髪を払いのけながら、月の明かりが差し込む窓を見やった。
「兄さんの力は、解放運動を益々盛んにさせるでしょうね。」
「助かる命もある。だが、それに比例して死ぬ命もあるんだ。──私は、それを見たくない。」
オデッサは無言でマッシュを見詰めた。
マッシュも、今度は目を外さずに、彼女を見つめた。
二つの視線が複雑に入り混じり……やがて、オデッサは諦めたように吐息を吐いた。
「分かってはいたわ。昔から兄さんは頑固ですもの。──あなたはきっと、私が死んでも動きはしないのね。」
戯れ言のように笑って、彼女はシニカルな表情で視線を逸らした。
その先には、壁に張られた子供たちの習字後があった。
整った字ではない。皆四苦八苦して書いたような字である。
それでも、生き生きとしていた。
この字を……こんな子供達を守りたいと思う心は、同じなのに、結局平行線なのだ。交わる事はないのだ。
私は闘う道を取り、兄さんは守る道を取る。
闘う術のないせいで、大切な人を失った私は、闘う術を手にし。
闘う術を持っていた兄さんは、そのために──私を殺しかけて、闘う術を手放した。
「………………マッシュ=シルバーバーグ……私は、あなたを許したわけではないの。」
オデッサは、月明かりに照らされる壁を見つめて、囁く。
その声は、死の宣告のように、マッシュの胸を射抜いた。
「オデ……っ。」
「あなたの考えた策に見事はまって、あの人は捕らえられたわ。
私が必死に考えた、逃亡のための偽装結婚式も……あなたが見抜いて、あの人は………………殺された。」
剣を振り回して、彼の手を握って、そうして飛び出した先で待ち構えていた兵たちの矢を見た瞬間、オデッサは確かに絶望を感じたのだ。
でも、そこで負けるくらいなら、最初から計画などしなかった。無謀な夢を見やしなかった。
だから、オデッサは強行に突破したのだ。
その兵を支持するように立っていた兄の存在に気付いていながら。
「……………………。」
「そんな自分に後悔したの? マッシュ? それでここで隠居生活?」
せせら笑うように、オデッサは笑った。
あの時ほど、自分の力の無さを後悔したことはなかった。
マッシュの中の──自分の中にも流れるシルバーバーグの血を呪った事はなかった。
血に濡れたウェディングドレスを着て剣を振るう妹を見ても、マッシュは顔色一つ変え無かった。
それが、彼の正義だったからか、軍師であったからか。
「馬鹿にしないでっ!!」
びり、と響くような声であった。
静かなこの村には似つかわしくない、戦場を思い返させるような声であった。
マッシュはその声を聞いて、背中がしなるのを感じた。
彼女の怒号は、神経をぴりりと突き立てさせる。
思いもよらず、精神が研ぎ澄まされるのを感じた。
「私は、そんなことされても嬉しくないわっ! あなたが戦に嫌気がさすのは好きなようにすればいいっ!! カレッカの事件で後悔しようと、何をしようとも、そんなの私の知った事ではないわっ! だって、あなたは逃げたのだからっ! 闘えるのに、それを放棄したのだからっ!!」
馬鹿にしないでと、彼女は叫ぶ。
私は必死だった。そして軍師に負けた。
ただそれだけのことだと、感情を抜きにして言える知識を持っている。
だけど、そういうのは許せない。
あなたが、自分のしたことを後悔して、こういう風に逃げるのは、許さない。
「………………さよなら。邪魔したわね。」
オデッサは軽く息をついて、踵を返す。
その背中を見送って、マッシュは何時の間にか詰めていた息を吐いた。
あれは、リーダーとして、上に立つものとしてふさわしい………………。
知らず握っていた筆を手放して、彼は苦笑いを口元に刻み込んだ。そして、軽く目を細めて見せる。
彼女の側に自分が立てば、解放軍は大きくなるだろう。それも見違える程早く。
けれど……ふとマッシュは自分の手のひらを見た。
先程の覇気を受けたためか、微かに震えていた。
それを握り締めて、マッシュは唇を噛み締める。
「でも……そうだとしても。」
そうだと、しても。
──眼裏に蘇る、少女の血に濡れた腕。
白く染まったウェディングドレス。
小さな少年の、口から零れた血の筋。
「忘れる事など……これ以上…………。」
できないから。
だから。
私は見ない振りをする。
彼女が戦を起こすのも、それによって人がさまざまな人生を歩むのも、見てみない振りをする。
例えこれが弱さだと言われても、ずるいと言われても。
もう──あんな思いをするのは、いやだったから。
だから見えない振りをする。
月明かりが差し込む部屋で、彼女の余韻を感じる気配すら見せず、彼はただ手を握り、自分に言い聞かせる。
「あなたは……何を考えておいでなのですか?」
そう尋ねた瞬間、男は、それを口にしたことを後悔した。
振りかえった少年の琥珀のひとみが、痛い。
「何、を?」
不思議そうに尋ねる声は、普通の少年のそれ。
けれど、彼はそうはとらなかった。
背筋がぞくりと震え、這うような恐怖に心が占められる。
「いいえ……今のは、聞かなかったことに──。」
おかしいのは、自分だ。
何を怖がっているのだろうか?
彼の瞳、彼の言葉──その一つ一つが、どうしてか胸に突き刺さる。
同じ年頃の少年に比べて、利発で正義感が強く──そして容貌が目を引き付ける。
けれどそれ以外は、普通の少年に見えるのに。
特にこれと言って素晴らしい資質を持っているように見えないのに。
なのに、どうしてかマッシュは、彼と目を合わせるたびに、胸にざわめきが宿るのを感じた。
これは、昔感じたことがあるような──そんな感じがする。
「変なマッシュさん?」
首を傾げて、彼はお茶を啜った。
本当に不思議そうなその声に、マッシュは苦笑いを覚える。
まったくもってそうだ。
自分だっておかしいと思うのだから。
この少年の一体何が、自分の心を震わせるのだろう?
何の変哲もない、普通の少年にしか見えないのに。
貴族の生まれのためか、木目細かな肌や、穏やかで優雅な仕草などが、品の良さを思わせる以外は──別に際立った者があるわけでもない。
あの妹のように、目を引き付け、心引かれる物を持っているわけでもない。
この国の皇帝のように、跪かずには言われないような雰囲気を有しているわけでもない。
なのに。
「………………。」
マッシュは何も言わず、先程この少年から渡されたイヤリングを見下ろす。
雫型のそれは、もう随分前に彼女がここに来たときに付けていた……彼女の形見。
これをどう読み取るのか──マッシュは一瞬ためらって、のほほんとしている少年を見た。
とてもではないが、彼はオデッサの死を看取って、悔しさをそのままにここに向かってきたようには見えなかった。
彼の従者らしい男や女の方が、心身ともに疲れきっているように見える。
一行のムードメーカーらしい屈強な男も、たまに下卑た冗談を言っては、男や女に突つかれているが、本当は大分心が消耗しているようであった。その目が、鋭く辺りを見回す所が、彼の油断の──余裕のなさを語っている。
少年はそれに気付いていないのか、このお茶おいしいですね、と微笑んでいた。
こんな少年にこれを──このような大切なものを渡すような妹であったかと、マッシュは思い返す。
けれど蘇ってくるのは、最後にあった彼女の姿ばかり。
怒声でもって、自分を震え上がらせた……妹。
ころり、と手のひらの上でそれを転がして、もう一度少年を見た。
彼は何やら面白そうに、隣に座る自分の保護者にちょっかいを出している。
くすくすと笑う顔は、年相応で、とてもではないが、オデッサが選んだとは思えないほど子供じみていた。
「ぼっちゃん! まったくもう、人様のおうちでお行儀が悪いですよっ!」
「今の状況だったら、どこに行っても人様のおうちじゃないか。」
「あ、それはそうですねぇ。とすると、人様のおうちでしかするしかないわけですよねぇ。」
「そうそう、そういうもんなんだよ。」
とぼけた調子で茶を持つグレミオに、うんうん、とスイが頷く。
その二人のやり取りを見ていたクレオが、やってられないとばかりに吐息づくと、ビクトールが苦笑を覚えて笑いかけた。
「あのなぁ、グレミオ、他人の家もなにも……こういうときにそういうのをやってる場合じゃないと思うんだが?」
「どういう時でもいたずらをかかさないのがぼっちゃんですから。」
きっぱりと応えて、グレミオは溜め息を零した。
その憂愁の吐息に、スイがムッと眉を顰める。
「ちょっと、それって褒めてるの? けなしてるの?」
「いやですねぇ、ぼっちゃん。私がぼっちゃんを褒める事はあれども、けなすことなどあるわけないじゃないですかっ!」
チカラを込めて言い放ったグレミオに、ふぅん、とスイは頷いて、
「なるほど、つまりそれが僕のイイトコロなわけだね。」
と、納得したように呟いた。
瞬間、グレミオとクレオが苦い顔で見合わせたが、スイは綺麗に見て見ぬふりをした。
その一連の会話を聞いていたマッシュは、ふと気付いた。
彼らの間に走っていた、ぴりぴりとした緊張感が全て消え失せているのに。
「……………………。」
はっ、としてマッシュはその中央で呑気にお茶を啜っているスイに目を移した。
彼はその視線を感じて、にっこりと笑った。
綺麗な──笑みであった。
それと同時に、マッシュの中に、何か恐ろしいものを見たときのような震えが起こった。
誰かを怖いと思ったのは、初めてであった。
「……僕が何かを考えてると思うのは、あなたの買い被りですよ。」
不意に、スイはマッシュの目を捕らえてそう呟く。
何のことかと思ったマッシュは、自分が先程口にした答えなのだと──気付いた。
スイはいたずらげな表情を宿して、笑った。
「僕はただ、見てきたものを知っているだけです。彼女に、自分の眼と心を信じろと言われただけです。」
まっすぐな瞳で、スイはマッシュを見つめた。
その目が、痛い。
その瞳が、視線が、苦しい。胸が焼き付くような感覚を覚えて、マッシュは軽く目を眇める。
「だから、これを届けにきたんですよ。」
しれっとして言ってのけるけど、彼が帝国にこの人ありと言われたテオ=マクドールの息子であることは、マッシュも知っている。
それなのに、いいのかと、尋ねたいけれど──彼の瞳がそれを許さない。
「受け取って下さいますね、マッシュさん?」
彼は、笑顔だった。
自分が何を持ってきたのか、知っているだろうに、彼は笑顔であった。
果たして、マッシュは彼の思う侭に答えるしかなかった。
「……私は、これを受け取れません。」
────────と。
少年が望んでいるであろう答えを返してやる。
すると彼は、驚く従者達を背後に、微かに微笑みを浮かべた。
オデッサの選んだ男が、自分の出した試験に合格したと、そう言いたげに……笑ったのであった。
オデッサの形見だと言われたイヤリングには、すでに弄られた後があった。
それは、オデッサが最後に持っていたにしては、おかしな跡であった。
レナンカンプ……オデッサが命を落したというその場所に、すでに崩れたという証──×印が刻まれているのだ。
誰の仕業かなんて、少し考えれば分かるはずであった。
そして、彼はこれが何を示すのか、分からぬほど馬鹿ではなかった。
ためらい、迷う自分を見て、彼はオデッサの遺言を任せるのには値しないと思ったのか、自分がオデッサに選ばれたと分かっていたのか、それはわからなかったけれど。
スイが迷いも無く選んだのは確かであった。
「いいよ、リーダーになる。」
彼が何を考えてそう言ったのか、きっと誰にもわかるまい。
その瞬間、奇妙な悪寒を感じたマッシュ以外は、誰にも理解できなかっただろう。
彼は、最初からその気だったのだろう。彼女からこのイヤリングを託されたときに、すでに覚悟していたに違いないのだ。
解放軍のリーダーになること。この地を帝国から解放するための先陣を切る事。彼はきっと、オデッサの死を看取った瞬間に、彼女から願いを託されたその時に、覚悟していたのだ。
無言でマッシュは空を見上げる。
結局、ここで得た落ち着いた平和な生活も、今夜限りの物となってしまった。
けれど、不思議なことに、妹が迎えに来たときは、死んでもここから離れはしないと想っていたのに、今はそんなことがない。
ただ心がすっきりしていた。
ここにいても結局戦いに巻き込まれると分かったからなのか、それとも──?
マッシュは無言で、最後になるであろう、我が家から見あげる夜空を見詰めた。
心が透き通っている。焦燥もとまどいもなかった。
これがどうしてなのか──マッシュはすでに答えが出ている気がしてならない。
白銀の月を見上げて、マッシュは目を細める。もう答えは出してしまったのだから、例えどんな答えが出たとしても、どうにもならないのには違いないのに。
「あ、満月〜。」
不意に上から声が降ってきて、彼はビクリと肩を震わせる。
「晴れてるからよく見えるね……マッシュさん。」
くすり、と笑い声すら含んで、窓から顔を覗かせたスイは、桟の上で両腕を組むようにして、顔を横にさせていた。
楽しそうに窓の下を見やったスイの顔を認めて、マッシュは驚いた表情を一瞬で隠した。
「……明日も早いですよ。」
この人は、自分の主となった人。
この人は──底知れない何かを有している気がしてならない人。
互いに信頼しあう関係を築かなくてはならないと、そうわかっているのに、マッシュは自然と身体が警戒するのを止められなかった。
彼の瞳に覗き込まれないように、気をしっかりひきしめないといけないと──そう考えてしまう。
「久しぶりのベッドだから、寝たいのはヤマヤマなんだけど……ね、そっちに行ってもいい?」
尋ねたスイに、マッシュは無言で彼を見あげて、苦笑にも似た微笑みを浮かべて見せた。
「どうぞ? 何もありませんけどね。」
「……──月が、見えるもの。」
微笑んで、スイは窓から飛び出す。
ひょい、と窓枠を飛び越えて、そのままマッシュの隣に降り立った。
その一部始終を見ていたマッシュは、何も言う気を無くして、溜め息を零した。
このオテンバぶりは、どこかの誰かに似ていた。
最も、彼は彼女とは違って、正真正銘男であったのだが。
「危ないですよ。」
「大丈夫だよ。家では、二階から飛び降りて遊んでたから。」
しれっと答えて、スイはマッシュに微笑みかける。
その笑みを受け取って、マッシュはまじまじと彼を見つめた。
月明かりに心細く映る白皙の肌。
今まで苦労などした事ないのだろう、綺麗な髪は漆黒につやつやと輝いていた。
何故かこの少年と、妹の姿が重なって、マッシュは緩くかぶりを振った。
今の彼を見て、テオ=マクドールの息子だと思うものはいないだろう。
それと同じ様に、あの時の彼女の姿を見て、これがあのシルバーバーグの娘だと思うものはいなかっただろう。
たわいのないことを思うたび、思いもせず彼女と彼を比べてしまう。解放軍のリーダーとして立った彼女が、会いに来て以来、会っていなかった彼女のことを──思い出す。
彼女は死ぬ寸前まで自分を許していなかった。
自分達を追いつめた「マッシュ」ではなく、力があるのにそれを出し惜しみしていたマッシュという男を、許す事はなかった。
「…………オデッサさんと、一緒に月を見たんだ。」
不意に、彼はマッシュと同じ様に月を見上げながら、そう囁いた。
マッシュは無言で幼いとも言える少年を見下ろす。
「サラディで──綺麗な月だったよ。彼女は、自分がどうしてリーダーになったのか、教えてくれた。」
「……──あれは、未だに私のことを許していないから。」
苦く笑いながら、マッシュが呟く。
少年が何もかもを知っているのだと、そう信じて疑っていなかった。
彼も軍人の子ならば、話は聞いた事があるはずだ。
そう遠くない昔……今から数年程昔の話だ。
帝国貴族の一人が反乱分子で、捕らえられたと言う話。そして、その婚約者が、せめて結婚式をと願いでて、それを使って逃げようとした事。──結局、シルバーバーグの者によって、その計画を看破され、反乱分子は死んだということ。
別に内密にされるようなことでもない。
この話は、当時悲恋話として、巷を騒がせたものだ。
その計画を見抜いて、貴族を死に追いやったのが、婚約者の兄であったことは、口には昇らなかったが。
マッシュは、その時には帝国を止めていたのだから……彼が力を貸していたなどと、誰にもわかるはずがなかったのだ。
「…………………………。」
無言でスイはマッシュを見あげる。
まるでその目が、妹のそれのようで──自分を攻めているようで、マッシュは無言で目を閉じた。
「……怖いの?」
そっと、スイの手のひらがマッシュの手を握る。
温かなそれに、マッシュはびくりと肩を震わせた。
見下ろした先で、スイが静かに瞳を向けている。
「こわい……とは?」
声が震えないように尋ねる。
怖いのは、彼の瞳。妹と良く似た光を宿す、この綺麗な眼差し。
この眼に見つめられるのが、怖い。何もかもを見透かされそうで、何もかもを持っていかれそうで、怖いのだ。
「自分のことが、わからなくて怖い? ──だから、逃げてるの?」
子供の言うことは、よくわからないと──そう笑い飛ばすことだってできた。
何を言っているのか分からないと、そういう事もできた。
でも、その瞳に捕らえられると、何も言えなくなる。
強い輝きの宿る瞳は、マッシュの心を鷲づかみにしている。
「……どれほど……どれほど人を傷付けたくないと思っても、血を流したくないと思っても──戦場に立つと、血を流して勝つことを考えているんですよ。」
掠れた声で、囁く。
それが、怖いのだと、マッシュは呟く。
地面が全て血で濡れた場所を、きっとこの少年は知らない。
その血に立って、自分の罪深さに恐れおののいたあの時を、彼は知らない。
なのにどうしてか、彼はそれすらも知っていると言いたげに……理解できると言いたげに、マッシュの手のひらを包み込むのだ。
彼の心を包み込もうとするかのように。──たぶん、無意識のうちで。
忘れたくても忘れられない過去というのは、誰にでもあるものだ。
マッシュにとって、それは同時に「軍師」である自分を捨てることであった。
大地が罪なき人の血で染まり、むせ返る血の匂いが──全て自分達の罪なのだと、そう知ったあの時であった。
それでも、軍師の座にしがみついたのは、このようなことを二度と起こさせてはならないと、そう思ったからであった。
もう二度とこのような──人間としてやってはいけないような策を作ってはならない、実行させてはならないと、そう思ったからこそ、無理にとどまっていた。
それでも、どうにもならなくて、叔父であり自分の師である男の考えを、厭い、恐れて──戦線を離脱した。
何もかもを忘れて、暮して行こうと、帝国軍から逃げ出した。そんなマッシュが、カレッカの事件で傷ついているのを知っていた者達は、何も言わなかったし、止めもしなかった。
いつか、傷がいえた時に戻ってくるのだろうと、そう想っていたのかもしれない。
「それが、……私の中のシルバーバーグの血なんです。──私の罪なんですよ。」
囁いたマッシュを、彼は無言で見あげる。
まるでそれが話の先を促しているようで、マッシュは視線に居たたまれなさを感じて、空を見上げた。
紺碧の空は晴れて澄み渡り、その中に、幾億もの星が縫い付けられるように光っていた。
月は鮮やかに輝き、中天から地上を見下ろしている。
頬を撫でる風には、土や木の匂いが混じっていた。
戦に嫌気が差し、逃げ出したマッシュを出迎え、癒してくれた土地。それがここであった。
それと同時に、そのマッシュを抱きしめてくれた土地でもあった。
生きていてもいいのだと、マッシュが感じた、場所であった。
正直な話、ここから出るのは、怖くもあった。包み込み、ここでなら自分は夜叉の仮面を脱げると──そう思っていたから。
その場所から出たら、自分は本当に戦場の夜叉になってしまうのだと…………。
「それは違うよ。マッシュ=シルバーバーグ。」
不意に、マッシュの手のひらを握り締めていた少年が囁く。
そのはっきりとした言葉に、マッシュはびくりと肩を揺らした。見下ろした先に、地上の星がある。
「血のせいにしてはいけない。家のせいにしてはいけない。──あなたは、あなたの望むままに生きる事を放棄しているだけだ。
逃げてるだけだよ。」
琥珀の瞳が、紅色に染まっていた。
それは、地上の星。紅い──凶星にも似た、鮮やかな星。
まるで血の色のようなそれを見て、マッシュは目頭が熱くなるのを感じた。
「逃げてる……確かに、私は逃げてるんですよ。」
逃げないと怖くて怖くてしょうがないから。他の誰でもない、自分が怖いから、逃げるのだ。
そうしないと、多くの人が死んでしまうから、自分のせいで、いなくなってしまうから。
「僕も怖いよ。──自分が何をしようとしてるのか知ってるからこそ、凄く怖い。」
スイは、静かに告げた。
けれど、その瞳が怖がっていない。
恐れていない。
「けれど、それでも僕は……見てしまったから。
それを見てみぬ振りをして、生きていく自分が──一番怖いって、そう思ったから。」
まっすぐな瞳だった。
マッシュの心を射抜くような、そんな瞳だった。
「だから、僕はここにいる。ここで決断した。──マッシュは?」
小さな手のひらを握り締めて、マッシュは再び空を見上げた。
そこにはただ月が在る。答えがあるわけではない。
それでも、見あげずにはいられなかった。
この村に、静かに居を構えて、数年がたった頃、彼らはやってきた。
帝国の抵抗分子らしき者が見つかった、が、証拠がない。反乱分子を捕らえるのに、あなたの策が欲しいと、そう願って。
おかしな話だと、最初は相手にしなかった。
自分はあの事件で、すでに帝国の部外者になっている身だ。何故今更──それも「マッシュ」を選ぶ必要があるのかと。
しかし、それにレオン=シルバーバーグが、あの鬼とも思える鬼才が乗り出すと聞いた瞬間に、マッシュはその誘いを受けた。
レオンは、最善の方法を選択する男だ。例えそれがどれほど人道に反していようとも、それが最善だと思えば、彼はそれを平然を行うのだ。勧めるのだ。
そんな男に、任せてはならないと、とっさにマッシュは思ったのだ。例えその裏に、どのような意図があろうとも、レオンにだけは──関わらせてはならないと。
──追いつめ、処刑まで持ってきて。なのにその男の婚約者とやらが「結婚式を挙げたい」と言ったとき、マッシュは咄嗟にそれが逃亡のための策だと、思い付いた。
だから、指示した。
そして、出てきた所を矢で射抜こうと──そう考えたマッシュの前に、飛び出してきたのは、ここ数年連絡を取っていなかった妹であった。
驚かなかったはずがない。
しかし、「軍師」としてのマッシュは命じていた。
「射て。」
──と。
血が飛び散り、オデッサが叫ぶのが聞こえた。
彼女のウェディングドレスが血にまみれ、それでも少女は剣を振るった。
その勇姿は、同時に痛くマッシュの胸に突き刺さった。
冷たくなっていく男を背後の庇いながら、それでも闘う少女を見ながら、マッシュは唐突に自分の失態に気付いたのだ。
オデッサが、男の婚約者であったから、帝国兵は、自分の元に来たのだ、と。
自分が、オデッサの兄である自分が、裏切っていないのだと──確認するために。
あの時本当なら、射れなどとは言わなかった方が良かったのだろう。
でも、マッシュはそう告げていた。
軍師として、策を握る人間として──告げていた。
そんな自分が、戦いなど嫌だと、自分の命令で血が流れるのは嫌だと、そう言ったくせに、いざ現場になると平然としている自分が、怖いと。
彼はそう思ったのだ。
今度こそ──マッシュは戦から離れた。
何もかもを封じて、動くまいと、そう思ったのだ。
その決意は、結局妹の死によって無くなる。
この少年の、いさぎよくも無謀な促しにより、無くなってしまう。
月を見上げてどれくらいの時間が立ったのか、マッシュにはもう分からなかった。
ただ肌に触れる風がヒヤリと冷たくて、身体を震わせて初めて我に返った。
未だ手のひらは、隣に立つ少年に奪われたままである。
さぞかし身体も冷えているのではないかと見下ろすと、彼は、はふ、と白く澄んだ息を吐き出して、同じ様に月を眺めていた。
その綺麗な横顔を眺めて、マッシュは唇を割った。
「あなたは、いいのですか?」
「……?」
スイは、ゆっくりとマッシュを見あげる。軽く目をしばたく様が、妙に子供めいて映った。
「リーダーをすること──本当にいいのですか?」
故郷と、父と対立する事がどれほど辛いのか、彼は分かっているだろうけど、きっと細かくは理解していないに違いない。
そう思って尋ねたマッシュに、スイは思いもよらず儚い表情を見せた。まるで闇に溶けそうだと──マッシュは咄嗟に彼の手を強く握った。
「後悔、したくないから。」
さまざまな思いをこめて、スイはそう囁いた。
その表情が、その微笑みが──覚悟を決めていた。
マッシュは無言で彼を見下ろし……そっと、笑った。
戦いは、いつも血が流れる。
戦いは、自分を夜叉に変える。
だから、怖い。だから、恐ろしい。
自分がいなくても、戦いは起きるだろう。怖いのは、その戦で自分が変る事、自分一人の考えで、敵も味方も、多くの者が死ぬということ。
でも。
「不思議ですね。逃げていても、結局後悔はするんですよ。」
長い間、逃げていて分かった事は、たったこれだけ。
10年近くも、見て見ぬふりを続けてきて、気付いたことがこれだけ。
それを気付かせたのは、後悔を押し付けて死んだ、妹だった。
恐怖が克服できたわけではない。
恐怖が無くなったわけではない。なのに、後悔だけは胸に巣食うのだ。
もしも、俺が彼女の側にいたら、彼女を殺させはしなかったのに──例えどんな手を使っても、あの子だけは生かしたのに、と。
そんな自分が怖いはずなのに、その強い思いだけが、今も心の内に巣食っている。
──馬鹿な娘だと、罵倒する内で、彼女の死を止められなかった自分を、責めている。
「だったら、一緒に立ち向って、後悔する? 例え勝っても、負けたとしても──僕たちは、どこかで必ず後悔するよ。後悔なんてしないって思っても、後悔する。」
スイは、わざとマッシュの手のひらを放して、正面から彼を見つめた。
長い間握っていた手のひらは、うっすらを汗ばんでいる。
けれど、もう震えてはいなかった。
彼の瞳も、怖くはなかった。
この目が射抜いているのが、自分の後悔の気持ちだと、自覚できたから。
──オデッサの言う事が、正しかったと、マッシュは未だに思えない。
才能があるのに、それを出し惜しみして、助ける人を助けられないのは、弱虫だと、そう激怒した彼女の言葉に従わなかったのは、良くなかっとは思わない。
けれども。
この才能があれば、彼女が助けられたことも確かなのだ。
彼女を助けられていたはずなのだ。──きっと。
「誰かを殺すことが戦だ。
人をこの手で殺す事は、いつも苦い思いがある。
けれど、それをしてでも僕たちは、幸せを追求したいと思ってる。幸せになって欲しい人達がいる。
幸せになりたいと、願ってる。」
スイは、右手のひらを差し出す。
オデッサに似た瞳の輝き。
でもこの少年のそれは、それよりもずっと確固たるものであった。
彼が背負う覚悟の分だけ、そうみせるのかもしれなかったけれども。
彼は、オデッサの言葉よりもずっと強く、マッシュの中に入ってくる。
彼女の信念は強かった。
そして彼の思いも強い。
何よりも彼は、オデッサよりもずっと、自分のことを理解している。この恐怖を、この後悔を、知っている。
「──あなたが、普通の少年には見えなくなりましたよ。」
軽口を叩くように、マッシュはその手を取った。
小さな、でも温かな手であった。
才能があることは、罪ではない。
才能を使わないことは、罪ではない。
「……………………一緒に、後悔する?」
くすり、と少年が笑う。
マッシュはそれに答えるように、頷いた。
「ええ、どこまでも──覚悟をしましょうか。」
二人は手をつないだまま、空を見上げた。
満開の星空に、一層輝くのは、満月。
怜悧な月を見上げて、マッシュは片割れの小さな主君に誓った。
今度は、逃げないと。
共に後悔するまで、後悔しても尚──戦い、勝利を手にして見せる、と。
「幸せになるのは、努力をしないとね。」
逃げて逃げて、幸せになろうと思ったマッシュは、その唐突なスイの台詞に、ぐ、と言葉に詰って、彼を見下ろした。
自分に向けられての台詞かと思ったが、彼の眼は遠くを見ていた。
逃げ続けても、結局は追いつめられるのだから。
だから、その前に──決断を。
その言葉が誰に向けられたものなのか、マッシュには分からなかった。
それでも、自分にも重い言葉だと言う事だけは確かであった。
逃げても、自分の才能が無くなるわけではない。
この帝国が、無くなるわけではない。
妹の死が、無くなるわけではない。
ならば、立ち向わなくてはいけないのだ。
大切な幸せを守るために──闘わなくてはいけないのだ。
そう。
「もう二度とあのような戦を起こさせぬためにも。」
「お前が、自分に狂い、恐怖に負けたときは……食らってやるよ。
僕が、お前に死をあげる。
お前のその恐怖から、解き放ってあげる。」
10000ヒット有り難うございます!
えーっと、マッシュと坊との間の信頼関係が生まれるまで……とのリクエストでございましたよね?
何故かオデッサが出張ってます。
更にこの二人の信頼関係を語ろうと思ったら、なんていうか──他の話とか関わってきたので、中途半端になってしまいました。
とりあえず、マッシュが坊に協力するまでの彼の心理などを……書いてみたのですが────、ど、どうでしょう? ビクビク
この二人の微妙な心理を表しきれず、やや後悔──。
こんなものでも良かったら、受けとってやって下さい〜。ううっ。
2000 9 18